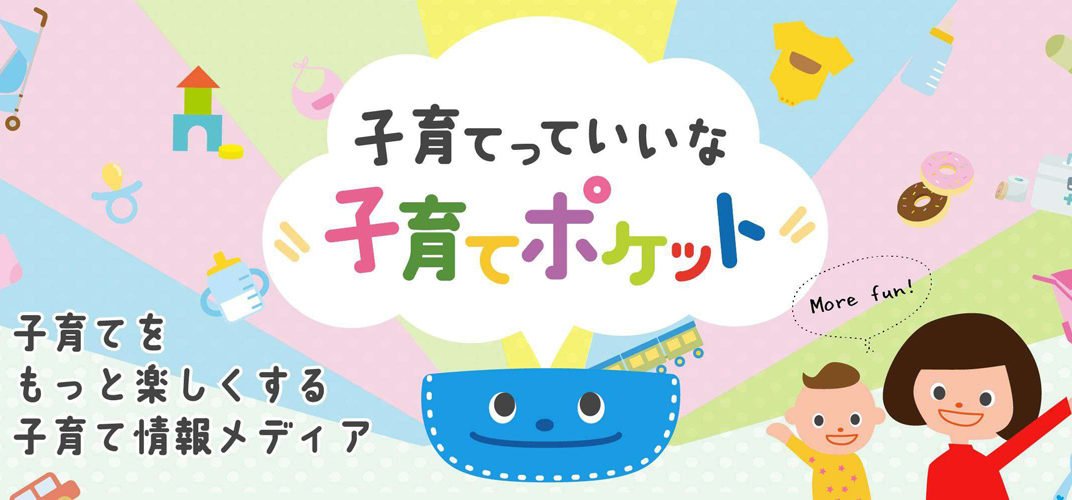1歳くらいになると、リズムや音に合わせて体を動かしたり、手を叩いたり、頭を振るなど、様々な反応が見られるようになります。
1対1で遊んでいる時、子どもに集中して欲しい時などに1歳児と楽しめる「手遊び」を知りたいと思いませんか?
今回は、保育士の新井先生がおすすめする1歳児さんも楽しめる手遊び歌の動画をご紹介します。手遊びのねらいについても解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。

2人の子どもの子育ても大分手を離れ、また小さな子どもたちの成長を見守りたく、みらいくに入職して1年が経ちました。 1人ひとりの子どもに寄り添い、毎日とびきりの笑顔をもらえることに幸せを感じながら、楽しく保育をさせてもらっています。
目次
1歳児をひきつける手遊び動画

手遊び・歌遊びにはいろいろな種類がありますが、まずは1歳児が夢中になれるおすすめの手遊び・歌遊びを教えてください!

どんな手遊びでも語り掛けるようにゆっくりとやれば、何を選んでもよいと思いますが、わかりやすく子どもと触れ合える手遊びがおすすめです。
1歳児におすすめの定番である手遊びや歌遊びをはじめ、保育園でも流行っている手遊び歌を、動画でご紹介します。
たっぷり1時間!手遊び動画

まずはこちら!たっぷり1時間、42曲の人気手遊びがつまったおすすめ動画です。
定番の「いないいないばぁ」や「まぁるいたまご」、人気キャラの「ピカチュウ」「ドラえもん」も登場しますよ。
人気手遊び歌メドレー動画はこちら
- さかながはねて
- りんごがコロコロ
- アイスクリーム
- キャベツのなかから
- オオカミとブタ
- はたらくくるま
- アンパンマンのおでかけ
- ウルトラマン
- こぶたがみちを
- アイスクリーム
- かきごおり
- ちょきちょきダンス
- ちょこれーと
- カミナリどん
- パンダ・うさぎ・コアラ
- まぁるいたまご
- あめふりくまのこ(パネルシアター)
- 七夕さま
- きらきらぼし
- はじまるよ
- おおきくなったら
- 大阪うまいもんのうた
- 三ツ矢サイダー
- ピクニック
- ディズニー手遊び
- コロコロたまご
- まほうのて
- ちいさなはたけ
- ワニのかぞく
- いわしのひらき
- ミックスジュース
- 3匹のこぶた
お誕生日会で楽しめる手遊び歌メドレー動画
- やまのおんがくか
- やきいもぐーちーぱー
- サンドイッチを作ろう(おべんとうばこのうた)
- ケーキを作ろう(グーチョキパーでなにつくろう)

手遊び歌をアレンジして、お誕生日会や季節のイベントを楽しむのもおすすめです。
保育園での手遊びのねらい

保育園で行う手遊びには、どのようなねらいがあるのでしょうか?
ねらい①コミュニケーションのため

手遊びには、さまざまなねらいがあります。
まずは、子どもたちが安心して園生活を送れるよう、子どもと保育士のコミュニケーションのためにやっています。
また、手遊びに自体に興味を持ってもらいたいとも思います。手遊びは言葉を獲得し、リズム感・音感・情緒を豊かにする助けにもなるからです。
ねらい②保育所生活に馴染んでもらうため
さらに、歌遊びや手遊びを保育の中に取り入れることで、知っている歌だ!先生の声がする!先生が楽しそう!この手遊びが聞こえてきたということはもうすぐ給食かな?など、生活シーンの中で安心感を持ってもらうことや保育所生活に馴染むこともねらいです。
保育士が手遊びをやって見せた時、子どもが一緒にやらなくても特に注意したり促したりする必要はありません。

様々な手遊びを毎日楽しく続けることで、少しずつ慣れ親しみ、自然と手や体が動くようになり、知っている言葉の部分だけを一緒に口ずさむようになります。
ねらい③子どもの気持ちの切り替えのため

手遊びは子どもの気持ちを切り替えてもらうためにやることもあるのですか?

あります。例えば、給食の準備で待っている時に本を読んで手遊びすると、給食への導入にもつながります。献立でバナナが出るとわかっている時は、バナナの手遊びをしたりしますよ。場面場面で手遊びを使い分けています。
0歳児・1歳児でも手遊びに参加できる?


手遊びには色々なねらいがあるのですね。手遊びは何歳からやっていますか?

保育園では0歳児クラスから手遊びをやっています。
0歳児クラスでも1歳から入園する子も多いので、1歳になる子は反応が早く、保育士の真似をして手遊びを覚えます。例えば6か月から入園する子はふれあい遊びから初めて、こちょこちょをして反応を見ます。

1歳だと話したり歌ったりするのがまだ難しいと思うのですが、1歳児は手遊びにどのように参加していますか?

1歳後半になるとお話できることも増えてきます。ところどころで自分の覚えた言葉を言う掛け合いに参加することもできます。
0歳児クラスで1歳になりたての頃は受け身です。個人差はありますが、1歳数か月になると反応が増えてきます。1歳児クラスでも、2歳になると一緒に歌えるようになり楽しんでいけますよ。
1歳児と手遊びをするときのコツ

0歳児や1歳児のなかには、手遊びの途中で飽きて違う遊びをしてしまったり、みんなが手遊びをしている中で違う遊びをしてしまったりする子がいます。
私としては、みんな一緒に手遊びを聞いて欲しいと思っていますが、保育園ではどのような工夫をしていますか?手遊びをする時のコツを教えてください!
大人自身が楽しみながら手遊びをする

保育園では、保育士自身が楽しむことを大切にしています。保育士である大人が楽しんでいると、子どもも一緒に楽しんでくれます。子どもの様子も見て、興味関心のあるものを取り入れましょう。
また、子どもによって興味は違うので、絶対やらせないといけないと思って手遊びをすると、それが子どもに伝わってしまいます。やはり一番は保育士自身が楽しむことで、子どもが違う遊びをしていても実は聞いていたり、関心を持っていたりするケースもあると思います。

大人も一緒に、楽しみながらやることが大事なのですね。
子どもの目を見てゆっくり行う

あとは、子どもの目をしっかり見て楽しそうにゆっくり行うことですね。
まだ1歳児になったばかりの子であれば、定番の手遊びを繰り返す、アレンジして子どもの名前やキャラクターの名前を取り入れるなどすると、より楽しんでもらえますよ。
「楽しいよ♪先生は元気だよ!みんなと遊びたいな」といった前向きな気持ちで、はっきりとした発音とゆっくりとしたスピードで行いましょう。
無料の動画サイトには、手遊びの練習できるも動画もあります。こうした動画を活用しながら、少しずつバリエーションを増やしておくいいですね。
1歳児と手遊びをする際のポイント

1歳前半くらいまでだと、まだ言葉を話したり歌を歌ったりはできないという印象がありますが、こうした1歳児とも手遊びを楽しむためのポイントはありますか?

確かにまだ小さな1歳前半の子どもの中には、じっと保育士を見ているだけで一緒にやらなかったり、できなかったり、保育士がやって見せてもその場からいなくなることもよくありますね。
しかし、子どもには手遊びや歌遊びをする保育士の声の調子や楽しそうな表情、リズミカルな言葉などは届いているのです。
心も脳も刺激を受け、いつか一緒に楽しめるようになる日が来ます。また、一緒にしなくても、見て楽しむことや、体の一部を動かして一緒にやっているつもりになる子どももいますよ。

子どもがまだわからないから、できないから、と思い込まずに、信頼関係を深めるきっかけやプロセスになると考えるとよいでしょう。
0歳児も1歳児もまだはっきり話しませんので、大人の語り掛けは、ほとんど独り言にようになってしまいます。それでも子どもはどんなに小さくてもしっかり聞いて、声の調子や表情から何を言っているのか理解しようとしているのです。

子守唄を聞くと心地よく寝入ったり、大好きなアニメの曲を聞くとテンションが上がったりするように、保育士の手遊びや歌遊びは、どんなに小さな月齢の子どもにとっても情緒が豊かになる上でとても有効な働きかけになるでしょう。
1歳児向けの手遊びの選び方

手遊びは、子どもとの信頼関係を作る上で重要なきっかけになるということがわかりました。では、1歳児さん向けには、どのような手遊びを選べばよいですか?

1歳を過ぎると、子どもたちが自分で考えることができるので、子どもたちに反応してもらえるようなものを取り入れるとよいでしょう。簡単でゆっくりできる手遊びがおすすめです。
例えば、「パン屋のお買い物である・ないを考えてもらう」「パン屋に食パンはある」「フライパンはある」と子どもに投げかけると、「あーる」「なーい」と子どもが反応してくれます。


1歳児には少し難しそうに感じますが…。

保育士が「あるかな、どうかな?」と問いかけてみると、子どもも一緒に考えてくれますよ。「なーい」とバツする手だけ真似してくれる子どももいて、その子なりに楽しんでくれます。
0歳の時は、ゆっくりはっきりとした手遊びをするようにしていますが、1歳になると同じ手遊びでもテンポを上げると喜ぶことがあります。子どもの発達に応じて反応を見ながら手遊びを選んでいます。
まとめ
今回は、「1歳児が楽しめる手遊び」や、1歳児と手遊びをする時のコツについて保育士の新井先生に答えていただきました。
子どもが大きくなるにつれて、「アルプス一万尺」「おちゃらか」「お寺の和尚さん」など、子ども同士でも複雑な手遊びを楽しめるようになっていきます。
子どもたちに「先生と遊ぶのが楽しい!手遊びって楽しい!保育園で楽しいな」と思ってもらえるよう、楽しく元気な笑顔で手遊びに取り組んでみましょう!
この記事を書いた人

長野県立大学健康発達学部こども学科1年の学生ライターです。大学では日々保育について勉強中。少しでも子育ての役に立つような情報をお届けしたいと思っています!